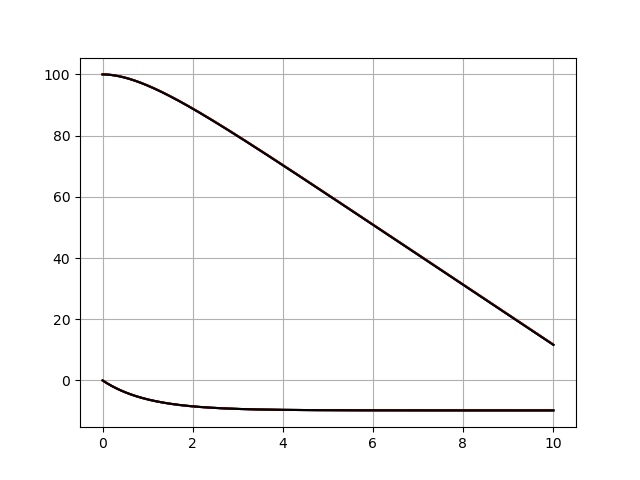力学の勉強をしていて、若い頃は向心力についての理解ができてなかったんだなぁと実感した。まぁ、分からずに居続けるよりは良いと気を取り直すことにする。
しかし、不思議なもので、力学の入門レベルの問題をじっくり解くのが楽しい。今の自分のレベルに合っているのだろうが、単に物理法則の理解を確認するためのものだけではなく、身の回りで起こる現象と絡めてあり、好奇心がそそられる問題があることも影響していると思う。これを「良問」というのだろうか。
電卓への入力ミスなどによる間違いが続くと、ちょっと嫌になるけど(笑)
力学に限ったことではないが、より難しい問題を楽しめるようになりたいものである…できるだけ早いうちに。